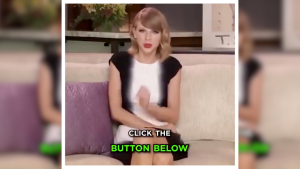過去と比べると現代は、インターネットによる比重が高い社会といえます。金融取引や情報発信など、あらゆる社会インフラがインターネットに接続されており、もはやインターネットがないと社会全体が成立しないといっても過言ではありません。特に情報発信は、テレビや新聞など特定のメディアからSNSなどを使った個人の時代に移り変わっています。そんなSNSやYouTubeを通じて誰もが情報を発信・拡散できますが、一方では迷惑系Youtuberや偽アカウントなどの有害なアカウントによる犯罪や被害が年々深刻になっています。近年、このようなアカウントが増加しているのには何か理由があるのでしょうか?この記事では、SNS上における有害アカウントが増える背景や現状を紹介しつつ、それらの見分け方や具体的な対応策などを、実例を交えて詳しく解説します。
なぜ、迷惑系Youtuberや偽アカウントなどの有害なアカウントが増えているのか?
ひと昔前まではFacebookがSNSの主流でしたが、最近はInstagramやX(旧Twitter)、TikTokなど画像や動画を使用したSNSが多くのユーザーに利用されています。また、YouTubeは、手軽に自分のチャンネルを作成できて一定数のチャンネル登録者数と再生数をクリアすれば、広告収入を得ることができるということもあり、近年多くのYoutuberが誕生しています。これらを利用する一部のユーザーは、いいね数やリツイート数などの拡散を最優先に考えて投稿したり、YouTubeの場合は広告収入を得るために再生回数やチャンネル登録者数の獲得を目指しています。ただ、フォロワーを増やすためやYouTube番組の再生回数を増やすために迷惑行為を実行するYoutuberや有害アカウントは世界各地に存在しており、日本でも度々迷惑行為を行なってニュースやSNSで話題になっています。また、他人から金銭や個人情報を盗む目的で作られた偽アカウントによる詐欺被害も増加の一途をたどっています。このような事件が増えている理由としては、もちろん社会におけるインターネットの浸透している部分が大きいといえますが、その他にも細かく分析していくといくつか理由が浮かび上がります。以下では、有害アカウントが増えている理由をいくつか紹介します。
SNSや動画で「目立てば儲かる」という構造
SNSやYouTubeは構造上、フォロワー数やチャンネル登録者数、動画の再生回数=影響力や収益となるため、数字を増やそうと犯罪行為を行なう有害アカウントが後を絶ちません。一般的に多くのユーザーが心理的に一定数のフォロワー数があると信頼しやすい傾向があることがわかっています。SNSの誕生以来、この人間の心理を悪用する悪質なアカウントが多く、様々な事件を引き起こしています。例えば、2022年には無名の健康系インフルエンサーがフォロワーを1万人以上「購入」し、企業案件を受注するなどして金銭的な利益を得たものの、実際の中身はほとんどボットだったことが判明しました。また、2024年1月にはInstagramで豪遊生活を発信しながら偽の出資を募っていた人物が詐欺容疑で逮捕されました。逮捕当時、容疑者はInstagramのフォロワーが11000人以上を抱えていましたが、もちろん投稿していた豪遊生活は嘘で、仲間と共謀しながら115人の被害者から約1億2400万円を騙し取っていました。さらに、若い女性を中心にSNSのライブ配信機能を使用してライブ中継を行なうライバーが増えています。視聴者は、投げ銭システムを利用してお気に入りのライバーに対してお金を支払うことができますが、あまりにもハマり過ぎて何百万円も投げ銭に使用してしまうユーザーがいたり、人気ライバーが視聴者にライブ中に殺されるという事件も起きています。このようにSNSである程度の数字を集めることで収益性が上がるという構造の悪用が目立ち、それに付随した事件も増えています。なかにはフォロワーや再生数を獲得できるのであれば、人を傷つけたり、犯罪行為も厭わないというユーザーも少なくなく、このSNSやYouTubeなどの構造自体が問題の一つであるといえます。
匿名性という責任のなさが悪用される
SNSの本来の特徴としては、本名や顔を出さずに投稿できる点です。そのため、サイバー犯罪者など悪意のあるユーザーが他人になりすまして誹謗中傷を行なったり、偽情報の拡散などが行なわれやすい環境にあるのが現状です。例えば、ある女子高生アイドルの偽アカウントが開設され、運営者になりすましてファンにDMで金銭要求して複数人が被害を受けた事件がありましたが、後に未成年者の犯行と判明しました。また、SNSでの匿名性を悪用して爆破予告や殺害予告の投稿もいくつか起きています。具体的には、学校や公共機関に対して「爆破する」や「殺す」といった書き込みを5ちゃんねるなどの匿名掲示板やSNSで投稿し、ターゲットとなった施設が一時閉鎖になったり、警察による膨大な調査コストが発生するなど社会的混乱が生じました。さらに過去には、X(旧Twitter)で自殺志願者を募って実際には9人が殺害されたという事件があったり、SNS上の誹謗中傷によって自殺に追い込まれたという事件も少なくありません。
AI技術の進化が「情報環境」を変えつつある
ここ数年ほどで生成AIや自然言語処理技術が急速に進化したことによって、SNS空間に新たなリスクが生まれています。最近、X(旧Twitter)やInstagramなどでAI生成による高精度なプロフィールや顔写真、人間のように自然な文章を投稿できる偽アカウントが急増しているため、本物なのかどうかを見分けるのが難しくなっています。特に有名人に本物そっくりに見せかけるディープフェイクと呼ばれる動画や音声などは影響力が高く、誰でも簡単に作れるようになったことで犯罪者が詐欺などに悪用しています。例えば、大量の偽アカウントを使って選挙や社会運動に介入して偽の多数派を作って印象操作して影響を与えることは既に世界各地で行われています。このように偽アカウントによる偽の情報の拡散によって、多くの人が混乱に陥る可能性があり、大変危険です。しかし、AIの技術は今後も驚くほどの速さで進化していくことが予想されており、AIか本物かを見極めるのが非常に難しくなるでしょう。
有害なアカウントの主な特徴
SNS上には、様々な形の偽アカウントと有害なアカウントが存在しますが、どれも一定のパターンや特徴があることがわかっています。以下では、有害なアカウントの主な特徴をまとめました。
ボット(bot)やスパム(Spam)
目的:自動投稿を使用して商品PRやURLを拡散
特徴:AI生成のアカウントが一斉に「新商品が当たる!」や「現金〇万円プレゼント」などと投稿し、詐欺サイトへ誘導
なりすまし
目的:有名人や企業を装って信頼を得る
特徴:SNSで著名な企業の「公式アカウント」を装って、IDとパスワードを入力させる偽のサイトを紹介
情報商材詐欺
目的:フォロワーに高額商材を売りつける
特徴:「自由に稼ぐ主婦」や「世界中を旅するフリーランサー」など一般的に憧れやすい人物を演じて、実際はリスクの高いFX教材などの高額商材に誘導
迷惑系YouTuber
目的:炎上商法で動画再生回数やリツイートなどのアクセス稼ぎ
特徴:店内で食品を無断開封・飲食、警察沙汰になるも「注目された」と開き直り
デマ拡散・分断煽動
目的:世論操作、混乱誘導
特徴:複数アカウントを使って「ワクチンで〇万人死亡」などといった出典不明な数字で不安を煽る
有害なアカウントの見分け方
こちらでは、有害なアカウントを見分けるための方法をいくつか紹介します。
プロフィール・投稿内容をチェック
有害なアカウントの特徴としては、プロフィール写真がAI生成の顔など不自然だったり、著名人の画像を流用していることが多いです。また、自己紹介に過剰な実績を明記していたり、投稿に「月収300万円達成!」や「フォローするだけで幸せに」といった過激な文言を多用している傾向があります。このようなアカウントの場合、投稿内容は他人のブログの記事を勝手に盗用していたり、アカウントの写真は海外サイトの画像からの盗用の場合がほとんどです。
投稿頻度・内容の偏り
投稿する時間帯や内容がパターン化している場合、ボットである可能性があります。また、フォロワーやいいね数は多いけれどもコメントがつかない、他のユーザーとのやりとりなどがないのも疑いのサインといえます。SNS上でよく目にする「有名人の感動名言bot」や「死ぬまでに見たい世界の絶景」などは、1日10~20回程度の投稿が自動化された拡散目的のアカウントです。
URLとドメインの確認
例えば、「スタバのギフト券が当たる」という投稿に使用されているドメインが、.xyzや.click、infoなどマイナーなドメインの場合には要注意です。特に長いURLや記号が多いリンクは詐欺サイトへの誘導の可能性が高く、この手口でこれまで多くのユーザーがログイン情報を盗まれています。
コメント欄や反応の不自然さ
再生回数が1000回、コメント数が500回など、SNSやYouTubeに投稿されている動画の再生数とコメント数が不自然なmでに合わない場合、有害なアカウントの可能性が高いです。特にコメントが「すごい!」や「最高です!」のような定型文ばかりの場合、アルバイトを雇って依頼した偽のコメントや自作自演の可能性があります。
有害なアカウントへの対応策
これまで様々な種類の有害なアカウントを紹介しましたが、今後も有害なアカウントは増え続けていくことが予想されます。SNSを使いながら有害なアカウントに遭遇しないための対策はないのでしょうか。以下では、有害なアカウントの対応策をまとめました。
怪しいリンクは絶対にクリックしない
SNS上の「〇万円稼げる!」や「豪華プレゼント」などの甘い言葉に騙されて怪しいクリックすることは絶対に避けましょう。また、知らないアカウントからDMが送られてきた場合も開いたり、返信はしないことをおすすめします。クリックや返信した場合、マルウェアに感染したり、個人情報が漏洩する危険があります。
公式マークの有無を確認する
X(旧Twitter)などの場合、公式に認証された公式マークが存在します。公式マークがある場合、信頼性は保証されるため、安心して情報を閲覧することができます。気になるアカウントをフォローする前に認証済みかをチェックしましょう。
Google画像検索を利用する
SNS上で気になるアカウントで使用されている画像をGoogle画像検索で逆検索することで、有害なアカウントかどうかを確認することができます。
ボット判定ツールを活用する
Botometerなどのボット判定ツールを活用することでボットかどうかを見分けることができます。
各SNSのプラットフォームの機能を使用する
XやInstagramでは、各アカウントに対して「スパムとして報告」や「ブロック」、「ミュート」機能を活用することができます。YouTubeの場合は、通報ボタンで「迷惑行為」や「なりすまし」「不快・暴力的」といったカテゴリーで運営に報告することができます。
セキュリティ対策ソフトを導入する
お使いのスマホやパソコンに高性能なセキュリティ対策ソフトを導入することも優れた対応策です。特にMcAfee社が提供しているマカフィー+は、有害なアカウントからユーザーを保護してくれるセキュリティ機能を複数使用することができます。特に自分で判断が難しい場合は、有効的な対応策といえるでしょう。
まとめ
今回は、SNS上での有害なアカウントが増えている理由をはじめ、有害なアカウントの主な特徴や見分け方、対応策について解説してきました。20年程前までSNSの世界は存在していませんでしたが、今では完全に市民権を獲得しており、SNSを通じて様々な交流が行なわれています。しかし、より利便性が高まるのと平行して有害なアカウントが増え、詐欺など多くの犯罪事件が起こっているのも事実です。特に生成AIによるディープフェイクを悪用した事件は今後一気に増加することが予想されており、注意が必要です。偽アカウントや迷惑系Youtuberなど有害なアカウントは増え続けており、普段SNSを利用している私達も気づかないうちに偽情報の拡散者にもなり得ます。個人情報の漏洩の被害に遭ったり、事件に巻き込まれないためにも、各SNSでフォローしたり、シェアする前に相手のプロフィールと投稿を確認する習慣を心がけることが大事です。たとえ、有名人と名乗るアカウントからDMが届いたとしても、偽物の可能性が高いため、添付された怪しいURLは絶対に開いてはいけません。もし、アクセスしようとしているサイトが本物かどうか自分で見分けがつかない場合は、マカフィー+のような優れたセキュリティ対策ソフトを導入すると、そのサイトの安全性をクリックする前に色分けで表示してくれるので安心です。SNS上に本物のように見える偽物があふれていますが、冷静な心と少しの疑問を持つことで被害を未然に防ぐことができます。快適にSNSを利用するためにも、まずは自分自身が正しい知識を身につけることが重要であり、一番の防御策といえるでしょう。